妊娠中は自分の体だけでなく、お腹の中の赤ちゃんの健康にも直結するため、食べ物の選び方はとても重要です。
特に注意が必要なのが「食品添加物」。
普段は気にせず口にしていても、妊婦さんにとっては胎児の発達に悪影響を及ぼす可能性があると指摘されるものも存在します。
本記事では、妊娠中に避けたい代表的な食品添加物とその理由、胎児への影響、そして無添加の食生活を実現するための工夫について詳しく解説します。
妊娠中に注意が必要な代表的な食品添加物とは

妊娠中に意識して避けたい食品添加物には、いくつか代表的なものがあります。
もちろん、国が定めた基準値以下であれば直ちに健康被害を引き起こすわけではありません。
しかし、妊娠中は体が敏感になっているうえ、赤ちゃんの成長段階に影響を与える可能性があるため、普段以上に注意が求められます。
保存料(ソルビン酸・安息香酸など)
食品を長持ちさせる目的で使用される保存料。
ソルビン酸や安息香酸はジュース、漬物、清涼飲料水に含まれることが多い成分です。
摂取しすぎると肝臓への負担が懸念されています。
人工甘味料(アスパルテーム・スクラロース)
カロリーオフや糖質オフ商品によく使われる人工甘味料。
妊娠糖尿病を気にして選ぶ人もいますが、一部の人工甘味料は胎児への安全性に関する研究が十分ではないため、極力控えるのが無難です。
着色料(タール色素など)
鮮やかな色合いを出すために使われるタール系色素。
特に菓子パンやスナック菓子に多用されています。
妊娠中に大量に摂るとアレルギーリスクを高める可能性が報告されています。
発色剤・漂白剤
ハムやソーセージの鮮やかな赤色を保つための発色剤、かまぼこなどの白さを出す漂白剤も妊娠中は控えたい添加物です。
👉 詳しくは「無添加調味料の選び方完全ガイド」の記事も参考にしてください。
食品添加物が胎児に与える可能性のある影響
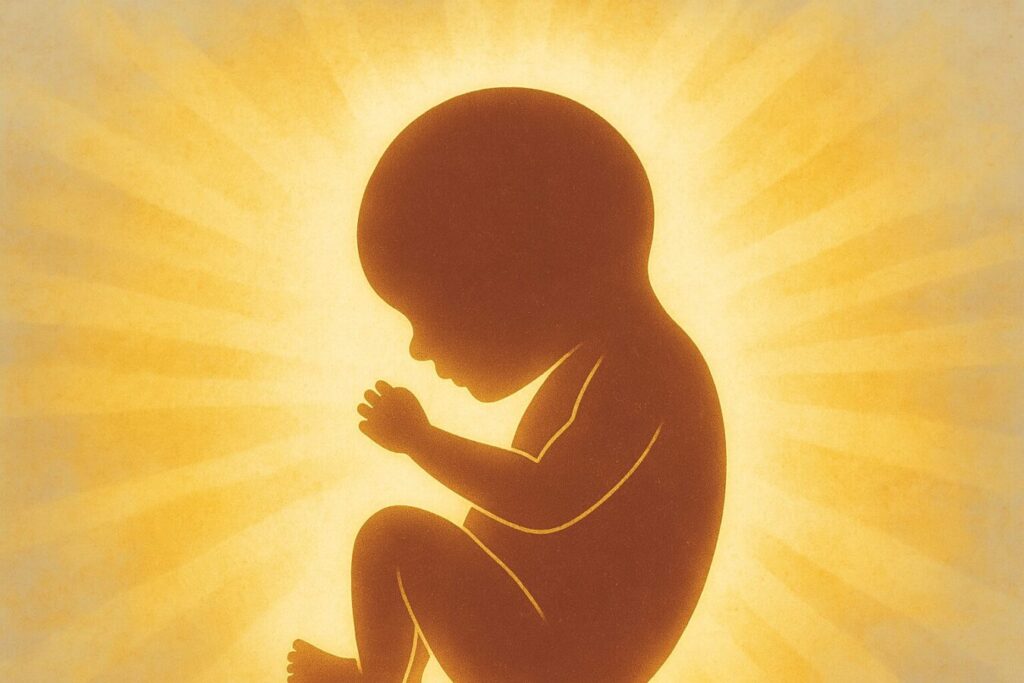
では、実際にこれらの添加物が胎児にどのような影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。
神経発達への影響
一部の動物実験や疫学研究では、人工甘味料や保存料の過剰摂取が神経発達に影響を与える可能性が示されています。特に脳が急速に発達する妊娠中期から後期は注意が必要です。
アレルギーリスクとの関連
タール色素や保存料の一部は、アトピー性皮膚炎や喘息などのアレルギー症状を悪化させる可能性があると指摘されています。
胎児期に母体が多く摂取すると、将来的なアレルギーリスクに関わる可能性が懸念されています。
腸内環境への影響
妊婦の腸内環境は免疫や栄養吸収に直結します。
食品添加物の一部は腸内細菌のバランスを崩す可能性があるため、妊娠中はよりナチュラルな食品選びが望まれます。
※厚生労働省 食品安全委員会も「妊娠中は食品添加物の過剰摂取を避け、バランスの良い食生活を心がけるように」と注意喚起しています。
妊娠中でも安心できる無添加食生活の工夫
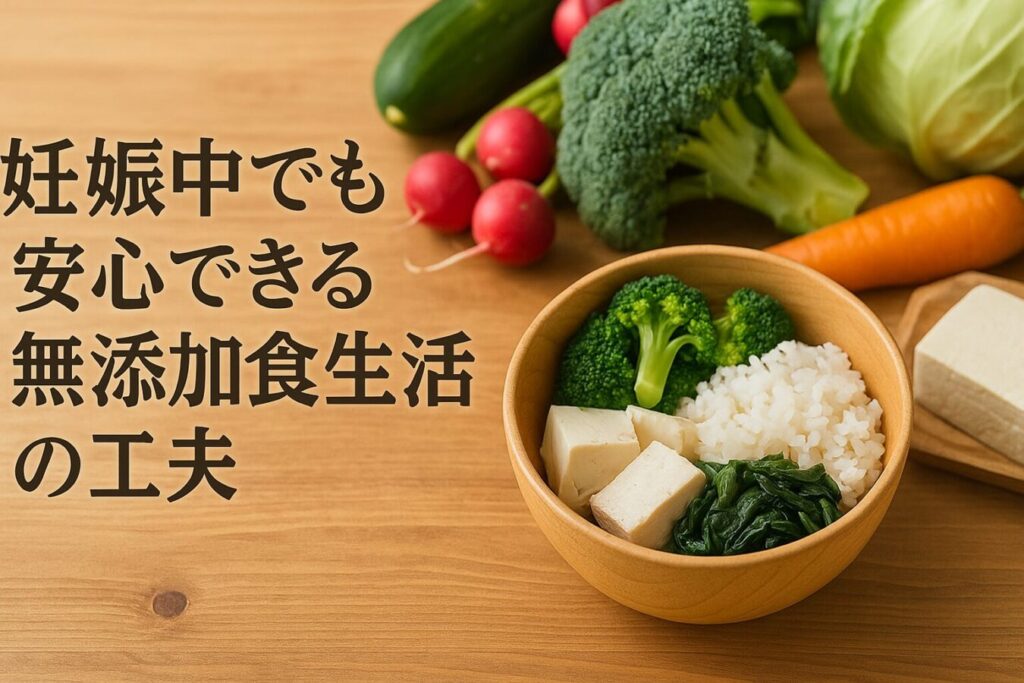
完全に添加物を排除することは難しいですが、日常の中で工夫すれば大幅に減らすことができます。
原材料表示ラベルのチェック方法
◆原材料がシンプル(「小麦粉・砂糖・塩」など少数)
◆カタカナの添加物名がずらっと並んでいない
◆「保存料不使用」「無添加」と明記された商品を優先
買い物の際に気を付けるポイント
◆スーパーでは加工品よりも野菜・果物・精肉など生鮮食品を中心に選ぶ
◆加工品を買うときはパッケージ裏を必ずチェック
◆「国産原材料使用」「オーガニック」マークがあると安心
外食・コンビニで選びたい食品例
◆コンビニ → サラダチキン(無添加タイプ)、冷凍野菜、無糖ヨーグルト
◆外食 → 和食中心の定食、焼き魚や煮物などシンプルな調理法
管理栄養士も推奨する無添加の暮らし方

最後に、管理栄養士の観点から「続けやすい無添加ライフ」の実践法を紹介します。
簡単にできる手作りレシピ
◆自家製ドレッシング(オリーブオイル+酢+塩)
◆手作りスープ(野菜・豆腐・だしでシンプルに)
無添加でも手に入る市販食品の紹介
- 無添加ソーセージ・ハム
- 国産大豆の豆腐
- 冷凍の有機野菜パック
続けやすい習慣作りのポイント
◆毎週「無添加デー」を決めて取り入れる
◆常備菜を作っておくとコンビニに頼らずに済む
◆家族と一緒にラベルチェックを習慣化すると継続しやすい
日本産婦人科医会も「妊娠中の食生活は添加物よりも、まずはバランスと安全性を重視すること」と推奨しています。そのうえで「可能な範囲で無添加食品を選ぶ」姿勢が安心につながります。
まとめ
妊娠中に避けたい食品添加物は、保存料・人工甘味料・着色料・発色剤など身近な食品に多く含まれています。
必ずしも完全に排除する必要はありませんが、赤ちゃんの健やかな成長を考えると、できるだけ減らす意識を持つことが大切です。
原材料ラベルを確認し、無添加やシンプルな食材を選ぶ工夫を取り入れましょう。
毎日の小さな積み重ねが、母体と胎児の健康を守る大きな一歩となります。
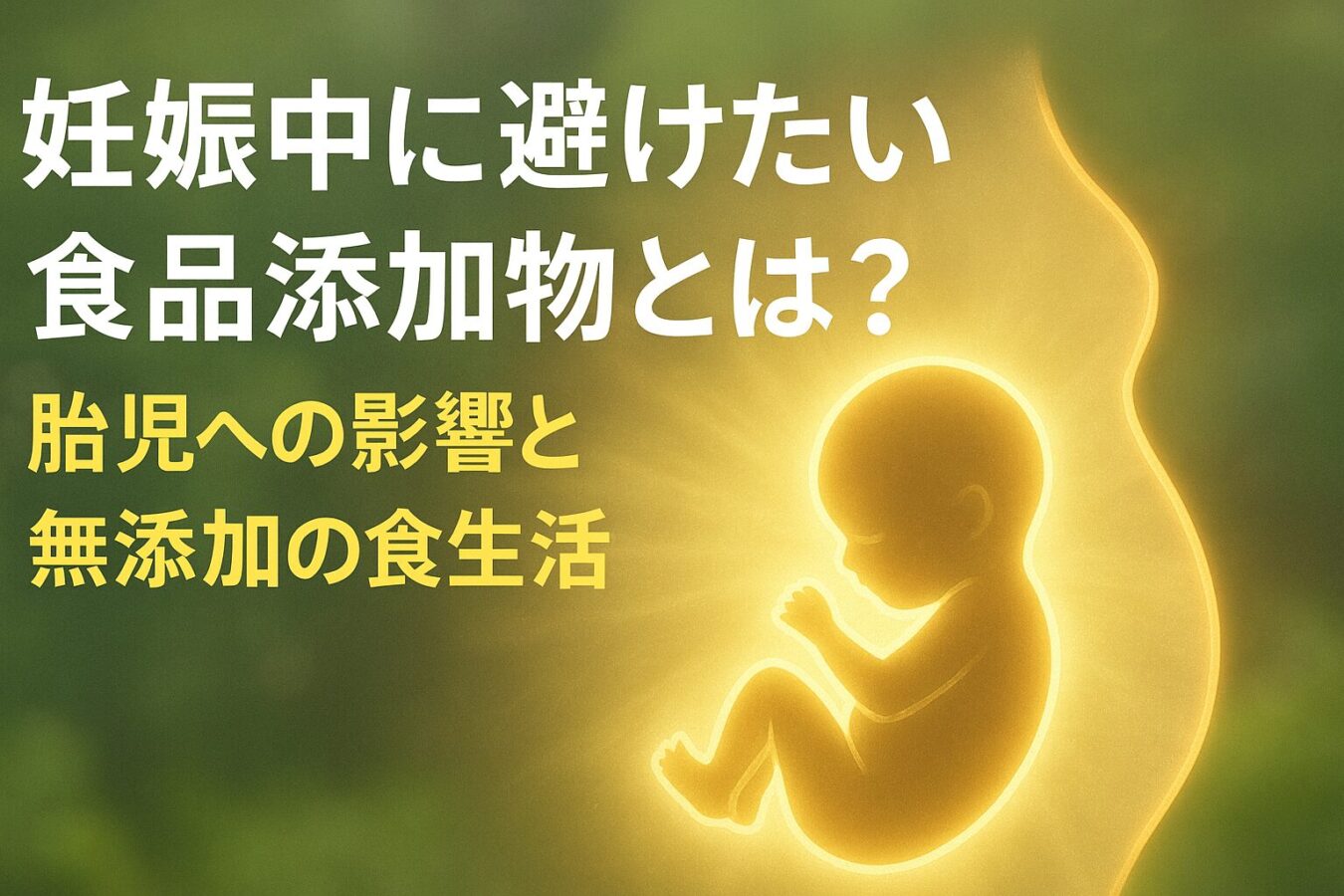
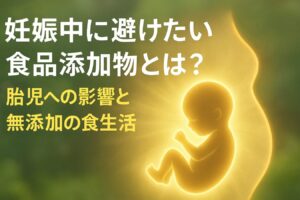
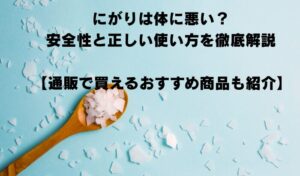





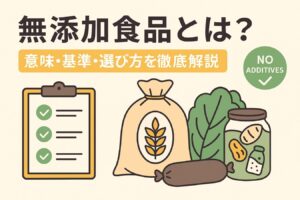
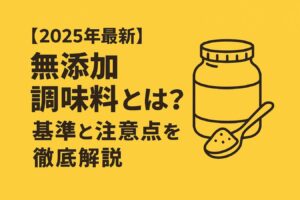
コメント