朝の食卓に潜む「食品添加物」、本当に危険なの?
みなさんは「食品添加物」と聞くとどんなイメージを持ちますか?
「体に悪そう」「化学的で不安」「できれば避けたい」…そんな声が多いですよね。
確かに「知らないと怖い」一面があるのは事実です。
ですが、一方で 食品添加物にはメリットもある のをご存じでしょうか。
例えば、食品を長持ちさせたり、見た目や味を良くして食欲をそそったり、あるいは不足しがちな栄養を補ったり。
私たちの食生活の裏で、食品添加物は大きな役割を果たしています。
もちろんデメリットやリスクも存在します。しかしそれは「無条件に危険」というよりも「正しく知り、上手に付き合う必要がある」ということ。
この記事では、食品添加物のメリットとデメリットの両面を徹底解説し、無添加志向の方でも納得できる「賢い食との付き合い方」をお伝えします。
食品添加物のメリットとは?

① 保存性を高めて食中毒や腐敗を防ぐ
保存料や酸化防止剤は、食品の腐敗や酸化を防ぎ、食の安全を守ります。
高温多湿な日本では特に重要で、コンビニのおにぎりやスーパーのお惣菜が翌日も食べられるのはそのおかげです。
② 見た目・味・食感を良くする
着色料や香料、乳化剤によって食品が鮮やかで香り豊かになり、食事が楽しくなります。
真っ白な豆腐やふわふわのパン、鮮やかなハムなども添加物が関係しています。
③ 栄養を強化できる
ビタミンやカルシウムなどを添加することで、不足しがちな栄養素を補えるのもメリット。
特に学校給食や高齢者施設では大切な役割です。
④ 品質を安定させて価格を守る
食品の味や香りを安定させ、供給や価格を維持する役割もあります。
保存期間が延びることでフードロス削減にもつながっています。
食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。
厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なう
おそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。
また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、
安全の確保に努めています。
食品添加物のデメリット

① 過剰摂取のリスク
加工食品やインスタント食品を多用すると、塩分・糖分・脂質と一緒に添加物も過剰に摂取する可能性があります。
② 複合的な影響は未知数
安全性は一つひとつの添加物ごとに確認されていますが、複数を同時に摂ったときの影響はまだ十分に分かっていません。
③ アレルギーや過敏症
保存料や甘味料に反応する人もおり、頭痛やかゆみ、体調不良の原因になることがあります。
④ 味覚の変化
人工甘味料や香料を長期間摂り続けると、本来の自然な甘みや香りを感じにくくなることがあります。
身近な食品に潜む添加物

実は、私たちが日常的に食べている食品にも多くの添加物が含まれています。
- 豆腐 → 凝固剤(にがりなど)
- 中華麺 → かんすい
- パン → イーストフード、乳化剤
- ゼリー → ゲル化剤、香料、着色料
- お菓子 → 膨張剤、人工甘味料
こうした加工食品を完全に避けることは難しいですよね。だからこそ「知って選ぶ」ことが大事なんです。
日本で認可されている食品添加物
日本で認可されて使用できる添加物や品質や使用量、食品への表示を説明します。
使用できる添加物
厚生労働省の発表では食品添加物には、食品衛生法によりルールが定められています。
使用できる食品添加物は、原則として厚生労働大臣が指定したものだけです。
これは、天然物であるかどうかに関わりません。
例外的に、指定を受けずに使用できるのは既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物だけです。
未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等はできません。
品質や使用量
食品添加物には、純度や成分についての規格や使用できる量などの基準が定められています。
食品への表示
原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示しなくてはなりません。
表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、
その用途名も併記しなければなりません。
表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。
避けたほうがよい食品添加物 7選
ここでは、摂取を避けた方が良い食品添加物を7つ紹介します。
亜硝酸ナトリウム(発色剤)

亜硝酸ナトリウムが使われている主な食品
・ハム・ソーセージなどの食肉製品
・鯨肉ベーコン
・魚肉ハム・ソーセージ
・いくら
・すじこ
・たらこ
アスパルテーム(合成甘味料)

アスパルテームが使われている主な食品
・ダイエットコーラ
・甘さを抑えたコーヒーシュガー
・歯磨き粉
・チューイングガム
・アイスクリーム
アセスルファムカリウム(合成甘味料)

アセスルファムカリウムが使われている主な食品
・飲料を中心
・チューイングガム
・キャンデー
・ジャム
・佃煮
・麺つゆなど、食品全般で広く利用
タール色素(合成着色料)

タール色素が使われている主な食品
・菓子パン
・チョコレート
・ゼリー
・ガムなどのお菓子
・たくあん、紅ショウガなどの漬物
・その他にも幅広い食品に使用
安息香酸ナトリウム(合成保存料)

安息香酸ナトリウムが使われている主な食品
・キャビア
・マーガリン
・清涼飲料水
・シロップ
・しょう油
・菓子製造用の果実ペースト及び果汁にも使用
ソルビン酸カリウム(合成保存料)

ソルビン酸カリウムが使われている主な食品
・かまぼこ、ちくわ、はんぺんなどの練り物
・ハム、ソーセージなど加工品
・お漬け物
・ワイン
・チーズ
・ジャムなど
OPP、TBZ(防カビ剤)

OPP・TBZが使われている主な食品
・柑橘類
・バナナ など
一部の添加物には安全性の懸念があり、健康被害が指摘されている。
食品添加物は、自然界にある植物由来の安全な香料なども含まれますが人工的に作られた合成物です。
その中には、安全性が指摘されている物質もありWHOでも警鐘を鳴らしているものもあります。
また、味覚障害などの報告もあり全く安全とは言い切れない部分もあります。
添加物を多く含む加工食品を多く摂取すると、栄養のバランスが崩れる可能性がある。

加工食品にはほとんど食品添加物が含まれています。
インスタント食品やジャンクフード菓子類などを多く摂取すると吸収する栄養素を阻害します。
また、栄養のバランスが崩れまたホルモンや免疫力を低下させる働きもあるため注意が必要です。
アレルギーの原因となる添加物がある。

食品添加物は、アレルギーの原因とされている物質も含まれているものが多くあり、摂取する際には
裏の表示をよく見て購入する必要があります。
しかし、表示義務がないものもあり、注意が必要です。
無添加志向の方におすすめの工夫

ラベルを読む習慣をつける
裏面表示にカタカナが多い食品は注意。まずは「知ること」から始めましょう。
調味料を無添加に変える
醤油や味噌、塩などの基本調味料を無添加にするだけで、家庭全体の添加物を大幅に減らせます。
手作りやシンプルな食品を選ぶ
おにぎり、ゆで卵、蒸し野菜などシンプルなものを意識して取り入れると安心です。
バランスを意識する
外食や加工食品に頼った翌日は、野菜や発酵食品を多めに。腸内環境を整える工夫も大切です。
まとめ
食品添加物には、メリットもデメリットもあります。
- メリット:保存性向上、風味改善、栄養補強、価格安定
- デメリット:過剰摂取リスク、複合的影響の不明確さ、アレルギーや味覚変化
大切なのは「全部避ける」か「気にせず食べる」かではなく、“バランスよく賢く選ぶ” こと。
無添加を意識しながら、必要な場面では添加物の力を借りる。その柔軟さが、健康で安心な食生活を守る秘訣です。
明日の買い物から、ぜひラベルを見て「本当に必要かどうか」考えてみてくださいね。
記事の全記事一覧ページを見るには こちらからcheck!
記事の細分化したカテゴリーページを見るには こちらからcheck!
オーガニック・薬膳 ランチレストラン・カフェ【東京】ページを見るには こちらからcheck!
オーガニック・薬膳 ランチレストラン・カフェ【大阪】ページを見るには こちらからcheck!
ブログトップページを見るには こちらからcheck!
沖縄でオイルトリートメントと脱毛ならここ! ほぐ・ルル -リラクゼーション&ボディメンテナンス-
沖縄でLGBTQ身元引受サポートチームはここです! PONO那覇
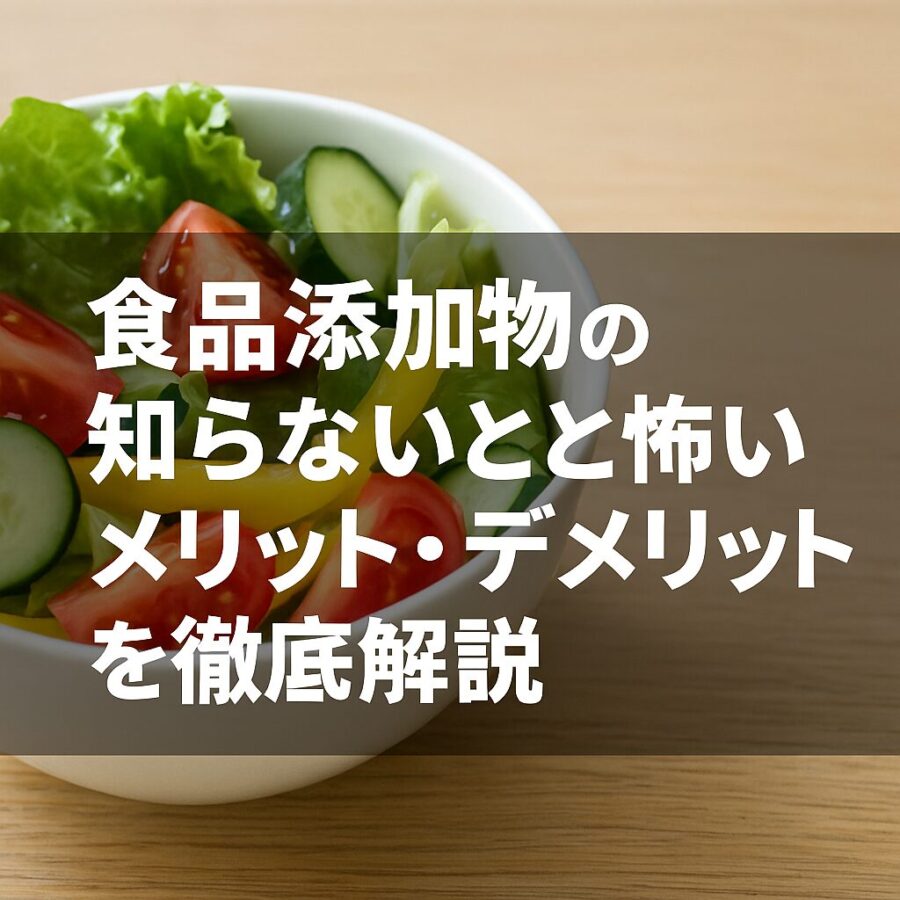
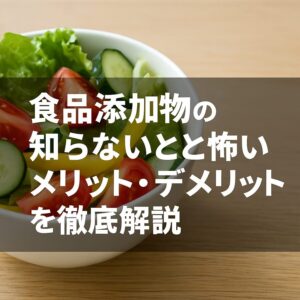
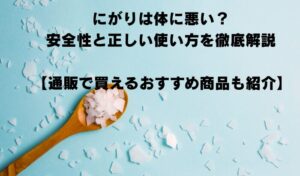
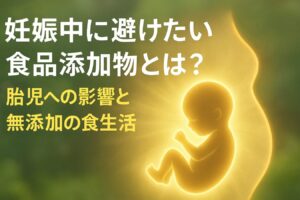

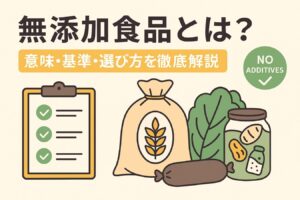
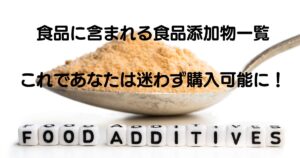


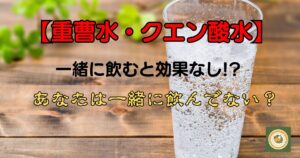
コメント